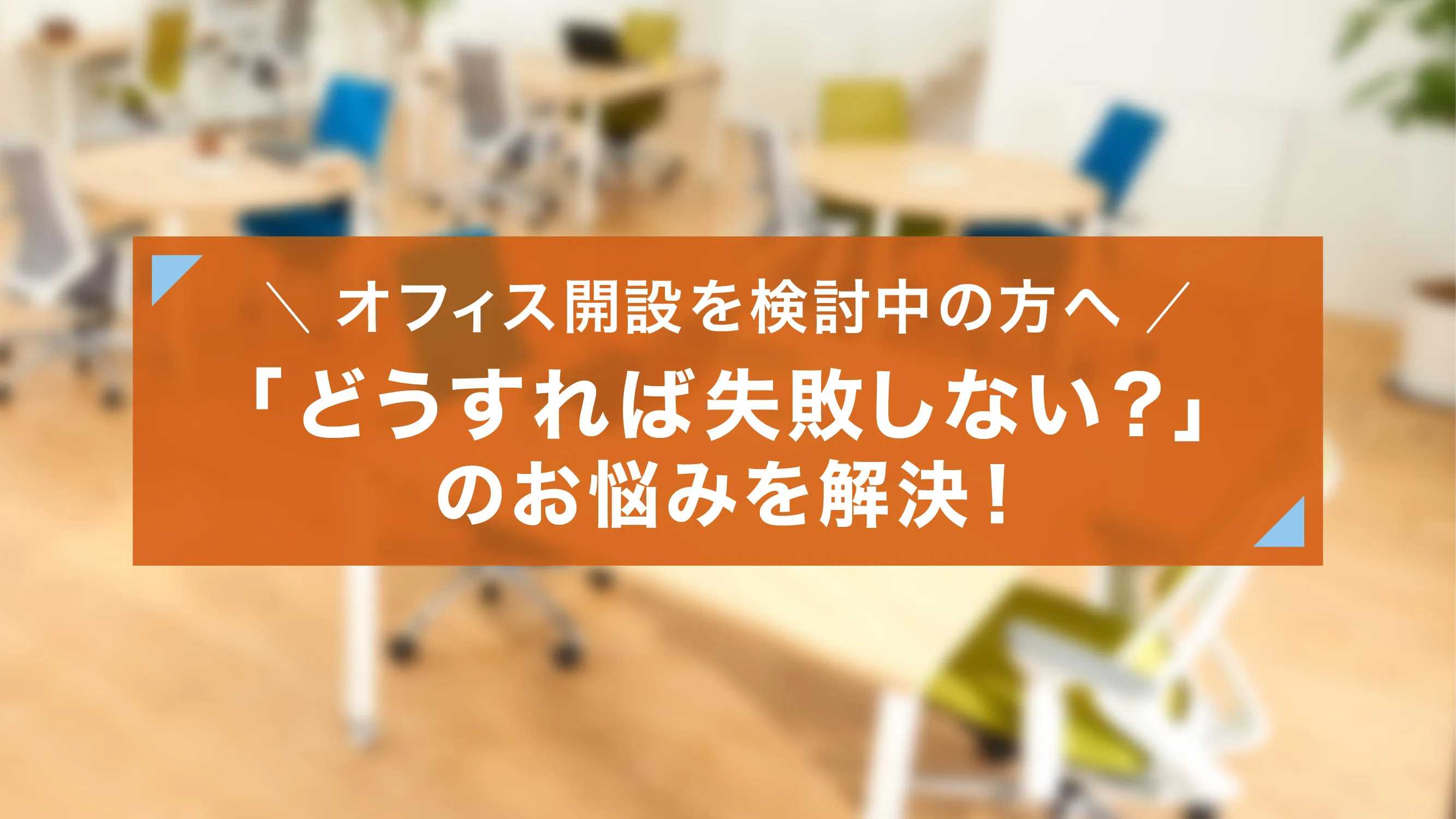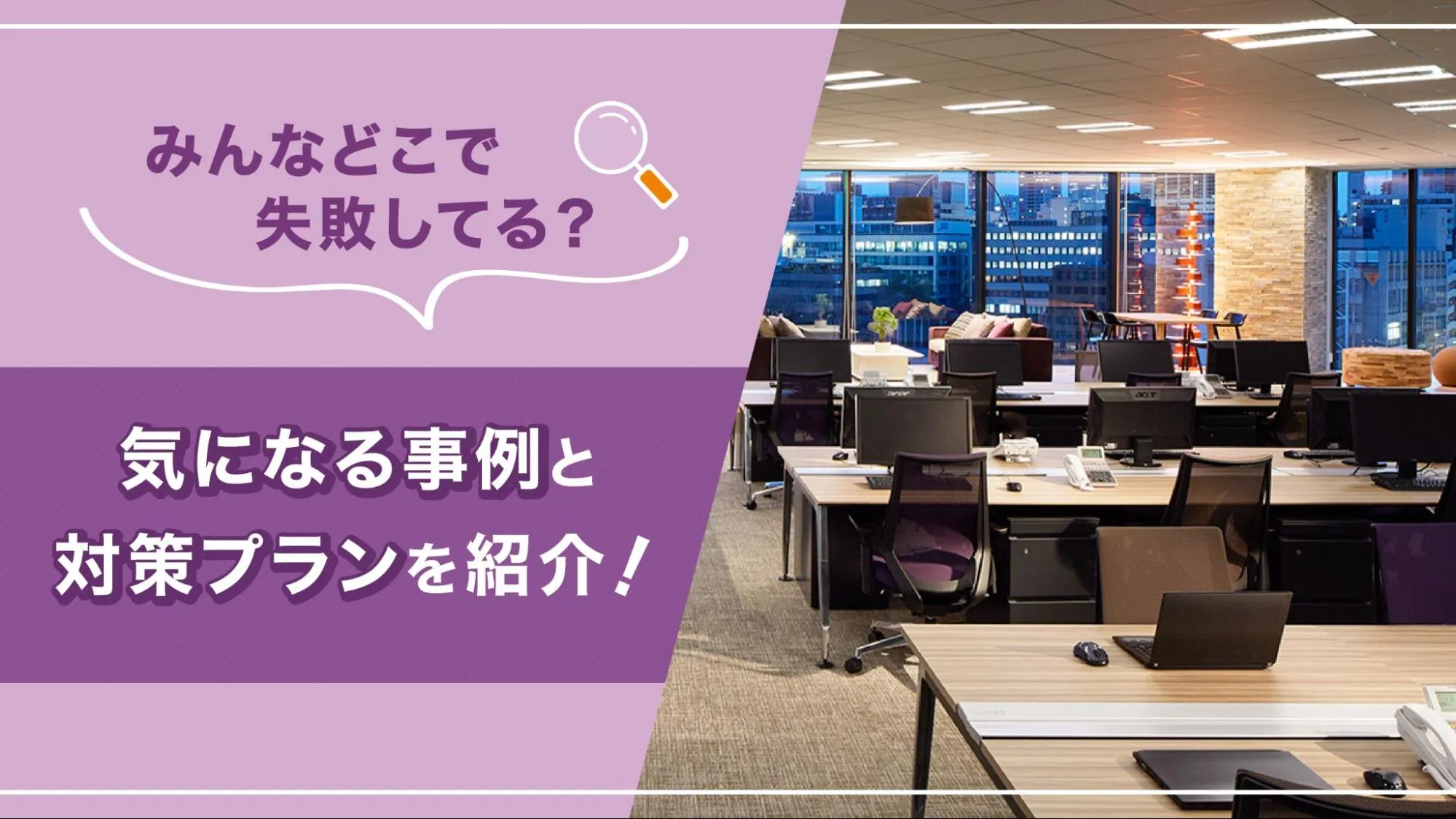- 2025.10.24
- オフィスリニューアル
【知っておきたい】フリーアドレスの失敗事例7選!すぐ検討できるプランも紹介

フリーアドレスを検討している総務・経営企画の担当者必見!
この記事では、7つの失敗例と改善策をお伝えし、レンタル導入でリスクを抑える方法を紹介します。
「失敗せずにフリーアドレスを実現したい」
とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
フリーアドレスの検討が増えている背景

多様な働き方の広がりとオフィス再設計ニーズ
テレワークやハイブリッドワークが一般化された昨今では、「全員が同じ時間に出社する」ということが当たり前ではなくなりました。
そこで、空席の多いオフィスをそのまま維持するよりも、スペースの有効活用や、柔軟に使える空間作りが求められています。
出社率の変化とスペース効率化の必要性
出社率が低下した企業では、固定席を維持すると面積の無駄になってしまうこともあります。
そこでフリーアドレスは、「限られた空間での効率化を図れるレイアウト戦略」として、注目されているのです。
生産性とコミュニケーションを高めたい企業の意図
座席を自由にすることで、部署を越えた交流や情報共有の促進を狙う企業も増えています。
「働き方改革」や「オフィスの再定義」を目的に、検討している担当者も多いのではないでしょうか。
よくあるフリーアドレスの失敗事例7選と原因を解説
フリーアドレスの検討が広がる一方で、導入後に「思った効果が出ない」「かえって非効率になった」と悩む企業も少なくありません。
ここでは、代表的な失敗例と、その背景にある原因を整理します。
1.導入目的の不明確さと形骸化
「とりあえず導入してみた」という動機で失敗するケースです。
目的が共有されていないため、結局はいつもと同じ席に座る固定化が発生してしまいます。
「働き方の自由度を高めたい」「スペースを効率化したい」など、導入目的を明確にし、評価指標とあわせて周知することが重要です。
2.ペーパーレス化が追いつかない
紙中心の業務フローが残ったままでは、席を移動するたびに資料やファイルの持ち運びが発生し、フリーアドレスが機能しないこともしばしば。
文書管理の電子化、スキャナの配置、共有ストレージのルール化など、インフラの一環としてペーパーレス化を同時に進める必要があります。
3.インフラ・設備整備の不足
電源不足、Wi-Fiの不安定さ、ロッカーや収納の不足は、日々の業務に直結するストレスを生みます。
見た目の刷新よりも、まずは「使える環境」の整備が先決。
想定利用人数とデバイス数に基づき、電源・通信・収納・防音といったインフラ設備を、設計段階で確保しましょう。

4.マネジメント・コミュニケーションの停滞
「部下がどこにいるかわからない」「新入社員のフォローが難しい」など、物理的距離が壁になってしまうケースもあります。
育成・相談が多い部署ほど影響が大きいため、所在把握の仕組み(ステータス表示や座席予約)や、指導・1on1の運用ルールをあらかじめ設計しておきましょう。
5.座席運用・ルールの曖昧さ
明確なルールがないと、「席取り合戦」や「いつも同じ人が同じ席を占有する」といった不公平感が生まれ、社員の不満につながります。
こちらも管理ツールの導入や、利用時間・清掃・荷物放置に関するガイドラインを定め、秩序ある運用を徹底することが重要です。
6.レイアウト・ゾーニングの設計ミス
集中スペースと会話エリアの線引きが曖昧だと、「話し声で集中できない」「打ち合わせの場所がない」といった不満も出てきます。
用途別にゾーンを明確化し、音・視線・動線を考慮した配置(吸音材、パーティション、ブースなど)も重要な観点です。
7.トップダウンの独断で決定
十分な説明や意見の吸い上げを行わずに導入すると、制度への不信感が根付き、定着の妨げになります。
対象部署のヒアリングや、社内での目的共有とフィードバック回収を通じて、合意形成を図ることが成功の前提です。
フリーアドレスで失敗しないための改善ポイント

上記のような失敗を避けて、フリーアドレス化を成功させたい!とお考えの方は、下記の要素を参考にしてください。
ここでは4つの改善ポイントを解説します。
1.導入目的を明確化し、全社員に共有する
「なぜフリーアドレスを導入するのか」を明文化し、社員全体に共有することから検討しましょう。
目的が共有されていれば、「自由な働き方を促したいのか」「スペースを効率化したいのか」といった意図が浸透し、ルール設定や評価基準にも納得感が生まれます。
結果的に、トップダウンによる独断導入も防ぐことができ、現場主導での改善が進みやすくなります。
2.ゾーニングとレイアウトを戦略的に設計する
フリーアドレスを単なる「席の自由化」と捉えるのではなく、業務内容に応じてゾーンを設計することが重要です。
集中作業に適した静かなエリア、打ち合わせや雑談がしやすい交流エリアなど、用途ごとに空間を分けることで、音や視線のストレスを軽減し、社員が目的に応じて自然に動けるオフィスになります。
また、レイアウトを定期的に見直し、部署の変化や組織成長に合わせて柔軟に調整する姿勢も大切です。
3.IT・設備環境を整える
ハード面の整備は、フリーアドレス運用の土台となる要素です。
十分な電源コンセントの配置、安定したWi-Fi環境、ノートPC・モニターの持ち運びやすさを考慮したレイアウトなど、日常業務をストレスなく行える環境を整えることが求められます。
さらに、社員一人ひとりの荷物量を想定し、ロッカーや個人収納スペースを確保することで、デスク周りの整理整頓がしやすくなり、全体の快適性が向上します。
4.運用ルールとサポート体制の整備
制度を「導入して終わり」にせず、運用フェーズでのルールとサポート体制を明確化することも意識しましょう。
たとえば、座席の利用時間や清掃ルール、チームごとのエリア運用方法を明文化することで、トラブルや不公平感を防ぐことができます。
制度よりも「それを支える運用設計」が、フリーアドレスを定着させる決め手です。
改善ポイントをいきなり実施するのは難しい?
理想的な仕組みを一度に整えることは、現実的には難しい場合も多いでしょう。
そこで注目されているのが、「まずは試してみて温度感を探る」という段階的な導入方法です。
たとえば、一部の部署やフロアだけで試験的にフリーアドレスを運用し、課題や改善点を洗い出してから全社展開することで、リスクを抑えながら最適な制度設計を進められます。
レンタル運用に注目!すぐに検討できるプランはこちらから
そこで、気軽に導入が可能で、自社に合っているのかお試し運用できるのが、レンタルサービスです。
もしマッチしなくても柔軟な変更が可能に。
万が一「うちはフリーアドレスにしなくていい」という判断になっても、大きなコストをかけずに変更・撤収できるのも魅力です。
どのような家具が必要なのかわかる
実運用を通じて、個人ロッカー・電源タップ・可動式ワゴン・モニターアームなど、本当に必要な備品が見えてきます。
カタログ検討では気づきにくい細部(高さ調整、キャスター有無、収納量など)に気付くのもポイント。
使い勝手を体感しながら最適化できます。
どのようなルールが必要なのかわかる
試験導入を始めると、席の占有・荷物放置・オンライン会議の音漏れなどのトラブルが可視化されます。
そこで、利用時間・清掃・予約・会話スペースの使い分けといった運用ルールを整備。現場の実情に合ったルールを策定できます。
どのようなレイアウトが最適かわかる
レンタルならレイアウト変更が前提。
集中ブース・打合せスペース・カフェエリアなどのゾーニングを入れ替え、動線や騒音の課題を検証できます。
複数パターンを試し、最もフィットする配置を、データと体感で決めることが可能です。
レイアウト失敗例の詳細については、下記の記事も参考になります。
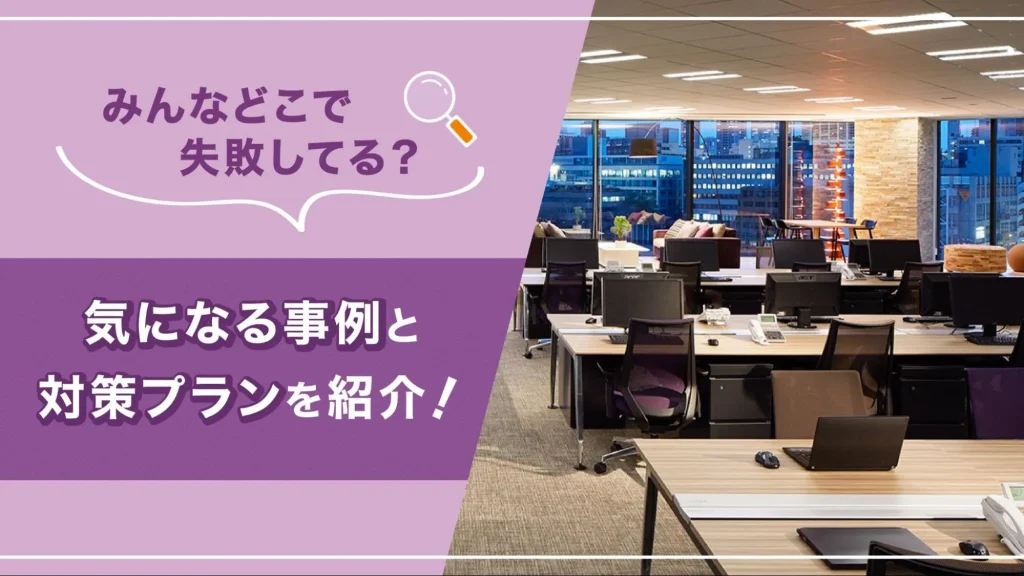
みんなの意見を反映しやすい
「お試し期間」を設けることで、現場の賛否や改善要望が集めやすくなります。
経営層の判断だけでなく、スタッフの声を反映してアップデートすることで、納得感の高いフリーアドレスが実現できるでしょう。
家具選びから搬入・設置までトータルサポートで対応
オフィスイッチでは、約2,000種類・100万点以上のアイテムから、最適な組み合わせをご提案。
お試し導入から本格運用まで、選定〜搬入設置の工程を一貫支援いたします。
必要に応じて、工事手配・当日の施工・現オフィスの原状回復も対応可能。
また、
「こんなイメージにしたい」
というご要望があれば、テーマに合わせたレイアウト提案も得意です。
例えば下記は、オフィス内に集中スペースを設置した「こもれるオフィス」

Problem:
1.ハイブリッドワークやWebミーティングが増えたことにより、会議室・簡易的なミーティングスペースが不足している。
2.社員の働き方にコミットしたオフィスをつくり、社員の幸福度を高めたい。
Solution:
1.ファミレスブースや個室ブースを配置したレイアウトで、「会議室が少ない問題」を解消。
2.多様な働き方にコミットし、生産性の向上や、アイディアの創出をサポート。
「オフィス内に集中スペースを導入したい」
というご要望には、こちらのプランが最適です。
こもれるオフィスの詳細はこちらから
上記の他にも、緑の多いフリーアドレス・アートな空間をテーマにしたフリーアドレスなどのプランもご用意しています。
このようなレイアウトまるごとのプランも、お試し導入からスタートが可能です。
フリーアドレスに失敗したくない方は、ぜひレンタルの活用をご検討ください。
お問い合わせはこちらから

記事監修者:郡 祐紀
企画推進室 Webマーケティングチーム
10年以上、企業のプロモーションやWeb制作、広告制作に従事し、2016年にコーユーレンティアに転職。
EC部門の売上拡大に取り組み、2024年からは新設されたWebマーケティングチームの責任者として、Web集客の陣頭指揮を執っている。